こんな方におすすめ
- 「大学職員 やめとけ」と検索される理由が知りたい
- 大学職員のメリット/デメリットが知りたい
- 大学職員に向いている/向いていないのか知りたい
大学職員に興味があり、検索してみたら「大学職員 やめとけ」の文字が…。一方で、「大学職員 高収入」「大学職員 ホワイト」という検索候補も出てきます。
高収入やホワイトは魅力的だけど、いざ入職してみて、やっぱり合わない・やりがいを感じずに早期に辞めたいと思ってしまっても困りますし、大学職員は採用枠が少ないので中々採用されなかったらどうしよう…と不安に思う方もいるのではないでしょうか。
入職後のミスマッチを防ぎ、就職・転職活動に参考になる「大学職員 やめとけ」と言われる理由を向き不向きも踏まえて現役の都内私立大学職員が説明します。
福利厚生もよく高収入を狙える職種だが、配属先部署による業務量の差や、自己成長がしにくい職場環境で悩むケースが多い!
「大学職員 やめとけ」と言われる理由7選
大学職員というと「公務員のようにルーティンの事務作業をしている職種」というイメージがあるのではないでしょうか。
一方で、検索結果には「やめとけ」や「やばい」といったワードが並んでいます。大学職員がネガティブに言われる理由は以下の7点です。
- 配属部署や担当によって業務量の差が大きいから
- 年功序列な組織体質だから
- 上司、同僚、教員、学生、保護者など関わる人が多いから
- 個人の成果や活躍は評価されにくいから
- 新しいことに挑戦しにくいから
- 少子化で教育業界がオワコンだから
- 自己成長の場が少ないから
いかがでしょうか。それぞれの項目について説明します。
配属部署や担当によって業務量や内容の差が大きいから
事務作業を希望していたのに学生対応ばかり、や、事務職員なのに出張が多く残業も多いなど、希望していた職務内容と異なる部署に配属されてしまう可能性があります。まず大学へ入職すると、各部署に配属されます。必ずしも面接で希望した部署に配属されるとは限りません。転職して入職しても前職と同じ仕事になることはほとんどありません。
下記に主な部署と職務内容をまとめました。部署名や内容は大学によって変わりますが大まかな部署名で記載しています。
法人管理系部署(人事・経理・庶務・総務・管理・施設など)
主に学校法人で働く職員や教授の支援や手続き関連を行う部署です。
管理や施設系は、技術職も多くグラウンドや施設の整備や備品の管理などを行います。
学校法人特有の寄付金や父母会を担当する部署は、卒業生や祖父母との関わりがあります。
人事や経理(繁忙期)は業務量が多いです。
学生支援部・教務部・就職キャリア支援部・留学国際関連・図書館など
特に学生・教授と関わることの多い部署です。国際関連部署は、留学生とも多く関わりがあります。
就職キャリア支援部は、企業との学内説明会を企画・実行したり学生の面接指導を行うこともあります。
教務部は特に業務量が多くなりがちです。
入学センター・研究支援・情報メディアなど
入学センターは学内の学生より高校生やその保護者と関わることの多い部署です。またイベントの企画や学外で説明会を行ったりと唯一出張の多い部署になります。
研究支援は教授と関わることが多く、研究費などの管理も行っています。情報メディアは、技術的な要素も必要になりますが、学生・教授ともに関わる機会があります。
入学センターは業務量が多く出張も多いです。
上記のように大学職員の部署は多岐にわたりますし、業務量の特に多い部署があります(人事・経理・教務・入試など)。適性や希望よりも人員不足や異動の関係で配属されることが多いため、希望にそぐわないことも多いのが事実です。
デスクワーク中心のコツコツとした作業を希望していても、学生部などの学生や教授とかかわる部署に配属されると、日々の中心が学生や教授の対応であなたの希望や得意を活かせずにストレスを感じてしまうかもしれません。
また、ワークライフバランスを期待して入職しても残業や業務量の多い部署に配属されてしまうと、希望がかなわずがっかりしてしまうでしょう。
部署によって内容や雰囲気が大きく変わるため、1つの学内で幅広い経験ができることはメリットに感じる方もいるかもしれません。
ただ、配属部署によりギャップを感じやすいため「やめとけ」と言われることもあります。
年功序列な組織体質だから
在籍年数が長いほど給与が高く役職も高いため、上司の給与と業績が伴っていないことで不満を感じてしまうことがあります。
大学は長い歴史を持っているところが多く、伝統的な企業や役所と同じように勤続年数に応じた給与体制が多いです。
一定の年数や年齢で役職が付くという点も同じです。
特に上司が高い能力がなく、部下に仕事を任せきりにしているということもよくある光景です。この場合でも上司と部下の給与は大きく差があるので、不満や苛立ちを感じてしまいます。
上司、同僚、教員、学生、保護者など関わる人が多いから
民間企業と異なり、気を遣う相手が多く、特にコミュニケーションに苦手意識を持っている人は気疲れしてしまいます。部署により関わる人は異なるものの、教員や学生、保護者など同僚や上司以外の人と関わる機会がどの部署も多いことは大学職員の特徴です。
また、業務を進めていくうえで上司のみならず教員を説得させることも必要になります。上司と教員の板挟みになってしまうことも…。
上司や教員との人間関係に悩んで退職してしまうケースも少なくありません。
個人の成果や活躍は評価されにくいから
大学は、個人の評価制度が整っていないことも多い業界です。事務職かつ組織単位での活動が多いため評価を行いづらく、また個人の実績を給与に反映させることもないため、業務に対するやりがいを感じにくいかもしれません。
最近では、評価制度を見直す動きも増えてきていますが、一般企業の営業職などと比べて組織単位の動きがメインのため評価されにくい傾向にあります。
新しいことに挑戦しにくいから
大学のような組織では、新しいことには挑戦しにくい傾向があります。
そもそも教育機関は、質の高い教育を提供し組織を存続させることを目的としているため、リスクの伴う新しいことには踏み出しにくいです。また、新規分野への決定には、多くの時間がかかるため簡単にはできません。
新しい事業への刺激を求める方には向いていないと言えます。
少子化で大学業界がオワコンだから
少子化による教育業界の将来性にリスクがあることも理由の一つです。
18歳人口の減少はとどまらず、この先も続くと言われています。国公立大学の統廃合や規模の小さい私立大学の廃学のニュースを目にすることも多いのではないでしょうか。大学業界も必ず安泰とは言い切れません。
大学の収入の多くは、入学検定料です。どの大学も入試を受けてもらおうと必死ですが、そもそも入試を受ける対象が少なくなれば収入が減ることは当然です。受験者数が減り入学者数の定員割れも多くなると学費も減り、経営が厳しくなります。
自己成長の場が少ないから
「仕事をしながらスキルを身に着けたい」、「スキルアップしたい」は大学職員では難しいです。事務職員の業務は誰でもできるような単調な仕事が多く、大学側も個人のスキルを獲得する援助などは行っていない場合が多いです。
よく言われるのが「大学に就職すると民間への転職が難しい」ということです。それは、大学で扱う業務は学校事務と言って特殊な業務が多く、民間企業では活かしにくくスキルが身についていないため面接などでアピールしにくいためです。
大学職員のメリット
「大学職員 やめとけ」と言われる7つの理由を挙げましたが、大学職員になる魅力やメリットはないのか、と思われるかもしれません。しかし、この7つの理由があっても大学職員になるべきメリットがあります。
大学職員のメリットは以下の5つです。
- 勤続年数に応じた高収入を得られる
- 定時に帰れる
- ワーママが多い
- 営業成績やノルマに追われることがない
- 休日・福利厚生が充実している
勤続年数に応じた高収入を得られる
大学職員は年功序列のため、勤め続ければ高い収入を得られることができます。国公立大学の平均年収は596万円、私立大学の平均年収は734万円となっています。
東京大学の平均年収をみると以下のような金額になります。
【事務・技術系】
平均年齢:45.2歳
平均年収:6,893千円(689万円)
2020年度ベースのモデル給与を見ていきましょう。
月額182,200円 年間給与2,718千円(22歳・大卒初任給)
月額324,920円 年間給与5,421千円(35歳・主任)
月額435,697円 年間給与7,340千円(50歳・マン副課長)
一方で私立大学の平均年収は734万円となっています。
明治大学の給与を例に挙げると以下のようなモデル給与となっています。
月額264,500円 年間給与4,761千円(大卒初任給)
月額335,300円 年間給与6,500千円(30歳・経験8年)
月額481,200円 年間給与9,100千円(40歳・経験18年)※諸手当込
こうしてみてみると日本トップの国立大学よりも私立大学の方が給与が高いことがわかります。特に明治大学は40歳で900万円を超えています!50歳には1千万円を超えていくと考えられますね。
このように大学職員は勤続年数に応じて高収入を狙うことが可能です。
定時で帰れる
ここは正直、部署によりますが終業時刻に帰宅する職員の方が圧倒的に多いです。比較的、忙しい部署と言われる「人事・経理(繁忙期)・教務・入試」は残業や休日出勤がありますが、そのほかの部署であれば定時で終わらせて帰宅することが可能です。
ただ、入学・進級のタイミングである3月~5月あたりは繁忙期にあたるため、残業になることもあります。
ワーママが多い
事務職員という職務内容もあってか意外と多いワーママ。職員には正規職員のほかに、派遣社員や契約社員、パートといった働き方をする人も多く、そのほとんどはワーママです。
正職員は産休・育休制度も整っていて働きやすいため、育休復帰後も働き続ける人が多い印象です。
営業成績やノルマに追われることがない
常に個人の営業成績を気にしながら仕事をすることがストレスとなっている方にはメリットと言えるでしょう。
業務上、個人の営業成績を求められたりノルマはありません。そのため同僚同士で競うこともなく、落ち着いた雰囲気で働くことができます。
もちろん、業務に期日や急に発生する仕事もありますが、数値として成績がついたり、それを責められるといったことがないので比較的おだやかな空気の中で働くことができます。
大学職員に向いている人の3つの特徴
ここまでお読みになり、「大学職員のメリットもわかったけど、自分は向いているのかな?働き続けられるかな?」と思ったのではないでしょうか。大学職員に向いている人の3つの特徴を以下に挙げました。
- コミュニケーションが得意な人
- ルーティンワークが好きな人
- 1つの職場に安定して働きたい人
コミュニケーションが得意な人
何度も記述しているように大学職員は、教員・学生・保護者・高校の進路担当など日々多くの人と接します。また業務も一人ではなく周りと相談しながら進めていくため、円滑なコミュニケーションが取れる方には楽しく業務をこなせるでしょう。
ルーティンワークが好きな人
大学の各部署で行う仕事は基本的に事務作業です。また古い体質が残っているためデジタル化されていなかったり、「え、こんなこと手作業でするの?」という仕事もあったりします。
実際に封筒に書類をひたすら入れ続けたり、資料をホチキスで留め続けたり…といった日もありました。
ルーティンワークや細かい作業が好きな人には向いている職業です。
1つの職場に安定して働きたい人
安定志向の人も大学職員向きです。メリットで挙げたように年功序列で給与が上がっていき、解雇されることもほとんどないので長く働き続けたい人にはぴったりです。
大学職員になると後悔する人の3つの特徴
一方で大学職員に向いていない人の特徴を3つ挙げます。
- 人とコミュニケーションを取るのが苦手な人
- 自分で仕事を仕切ったり、スキルを身に着けたい人
- リモートワークや在宅勤務を希望する人
人とコミュニケーションを取るのが苦手な人
まず、人とコミュニケーションを取るのが苦手な人・苦に感じる人には向いていません。
大学職員は多くの人と関わりながら仕事を進めるため、コミュニケーションが取れないと仕事が進まず、自身も苦に感じてしまいます。
自分で仕事を仕切ったり、スキルを身に着けたい人
大学職員は自分で仕切って仕事を進めたい人には向いていません。組織単位で目的を達成することが主なため、個人が突っ走っては周りからも反感を買ってしまうかもしれません。
また、単純な事務作業が多いため仕事でスキルを身に着けることは難しいです。これが大学職員から民間企業への転職が難しいと言われる理由です。
リモートワークや在宅勤務を希望する人
コロナの影響で、民間企業ではリモートワークや在宅勤務が増えましたが、大学職員は大学にいてできる業務がほとんどのためこのような働き方はできません。
授業や会議は遠隔で行う機会も増えてきましたが、コロナ禍と比べると遠隔授業の割合は劇的に減り学生も学内に戻ってきました。事務職員は学生対応や教員対応もあるため、リモートワークは難しく出社が必要になります。
大学職員に関する「よくある質問」
- 大学職員の仕事内容は?
-
管理系部署と大学ならではの部署の二つに分かれます。
【管理系部署】
総務・経理・人事など
【大学ならではの部署】
入試・教務・学生生活・就職・留学・図書館などの施設管理・研究費・同窓会など - 大学職員は正社員?
-
正職員と非正規職員(派遣・契約・パート)に分かれます。
非正規職員の仕事内容は、正職員とあまり変わらないこともありますがお休みや給与は雇用関係により異なることが注意です。
- 大学の繁忙期っていつ?
-
部署により異なりますが、3月~4月は繁忙期になると思います。卒業~入学で業務が一気に増えるためです。入試は10月~3月が繁忙期にあたり、4月は逆に落ち着く時期になります。
- お休みが多いって聞いたけど…
-
大学によります!
お盆や年末年始などの長期休みは比較的長いです。夏にお盆以外の休みのある大学もあります。ただ、土曜日や祝日が勤務がある大学も多いので帳尻合わせのため夏に休みが設定されていることが多いです。
※年間休日を計算すると、民間企業の方が多い場合も!
まとめ
「大学職員 やめとけ」と言われる理由をメリットや特徴などを踏まえて説明いたしました。いかがでしょうか。
配属部署による業務量や内容の差、人間関係や自己成長がしにくい職場環境で悩むケースが主な理由です。一方で勤続年数に応じて収入が上がる点やノルマがないなどのメリットもあります。
メリットでも述べたように、勤続年数により年収が上がるため安定的に長く働きたいひとには向いています。ワーママも多いので、女性にとっても働きやすい環境です。
「やめとけ」と言われる理由についても考えたうえで、メリットに魅力を感じたのならぜひ目指してみましょう!
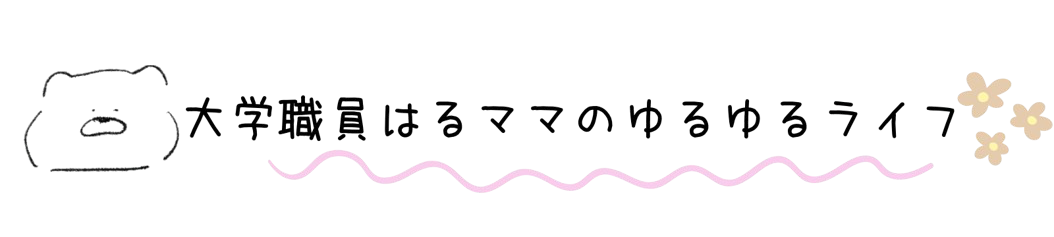
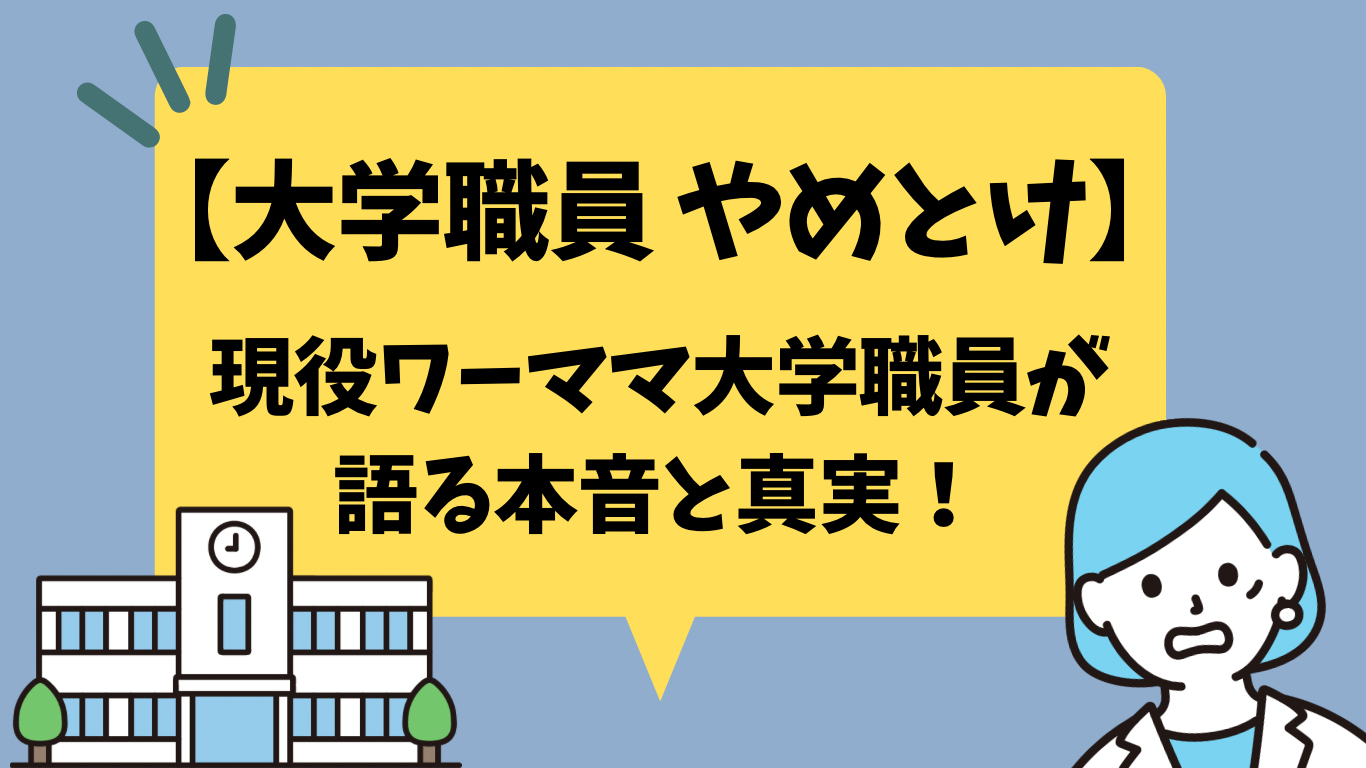
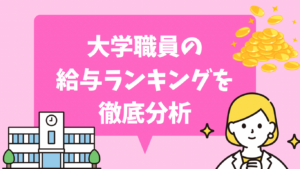
コメント